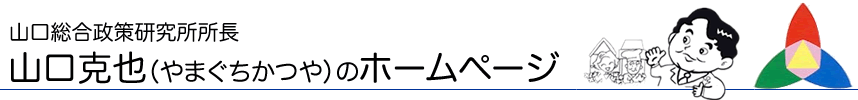岡本太郎が太陽の塔に託した思い
岡本敏子氏講演会資料
はじめに
戦後日本の美術界においてさまざまな絵画作品を生み出しながらも、単なる「画家」であることを常に拒否し、全人間的に「芸術家」でありつづけた岡本太郎氏に対する関心は、氏が1996年平成8年に84歳で亡くなられてからもますます高まっており、残された作品や著作は現在においても私達に強いメッセージを発しつづけています。特に私達吹田市に住む者は、氏の最大の作品太陽の塔を見るたびごとに、新たな感動を得ているということができるでしょう。
岡本太郎氏の作品は、オブジェについては氏が依頼をうけて製作された日本各地にありますが、油絵の多くは昨年10月に川崎市に完成した川崎市岡本太郎美術館に寄贈されており、また一部は生前のアトリエであった東京・青山にある岡本太郎記念館に収蔵されています。吹田市でもダスキン本社に陶板レリーフによる壁画「みつめあう-----愛」があり、一般の方でも見ることができます。私が太陽の塔美術館の必要性について語るとき、川崎市に既に岡本太郎さんの美術館があるのだから、わざわざ吹田市にもう一つつくる必要はないんじゃないか、といわれることがあります。私は川崎市の美術館にはもう何度も伺わせていただいており、非常によくできた展示にいつも感動して帰ってまいりますが、そのたびごとに、太郎さんはこの美術館で収まる人ではない。ここに収めてしまったら、吹田市や、大阪、西日本の若者達が岡本太郎氏の作品に直接触れて、氏のメッセージに気づく機会が失われてしまうと感じるのです。岡本氏が発信しつづけた芸術や人生についての考え方、メッセージはいまの方向性を失った日本に必要不可欠なものだからです。
今日の目的は、万博と岡本太郎氏に沢山の思い出を持ってくださっている会場の皆さんとこのメッセージについて一緒に考えることにあります。私ども太陽の塔美術館を求める市民の会は、岡本太郎氏の芸術が大変重要であり、その作品をあつめた美術館は多くの人にとって大変な価値のあるもので、美術館の存在が吹田、大阪のまちづくりに大きく役立つと考えています。今日皆様に同じ思いを感じていただければ無上の幸せです。岡本太郎氏の芸術世界はとても大きく、岡本敏子様の力をお借りしても、2時間の講演会のなかで、皆様に充分御説明ができるとはとても思えませんが、これを一つの機会にして、皆様方それぞれが、氏の作品や著作に触れていただければという思いで講演会を企画させて頂きました。不充分な点が多々あろうとは思いますが御容赦を宜しくお願い致します。
芸術の価値とは何か・日本芸術と西洋芸術の出会い
芸術はその時代、地域の世界観や理想の生活についての思い、価値観に基づいて制作されています。岡本太郎氏の活動を50年にわたって支えられ、太郎さんの養女になられた岡本敏子氏も、岡本太郎は芸術を生きること、生きている意味を示すこと、宇宙観を示すことと考えられていたと述べておられます。そのため、全く異なる二つの文化が出会ったとき、芸術においても、価値観の差に起因する大きな対立がおこります。明治維新から現代にいたる日本芸術の混乱は、日本の社会が西洋文明と日本文明という二つの文明がもつ、価値観の位置付けと調和を見出せないために起こったことなのでしょう。岡本太郎の前期の作品にも、西欧文明と日本文明の対立のなかで、苦闘する芸術家の姿が見えます。岡本太郎の作品の位置付けを考えるために重要な西洋美術と日本芸術の出会いについて述べたいと思います。
日本の芸術と西洋の芸術が初めて本格的に出会ったのは1867年のパリ万国博覧会でした。1853年のペリー来航以来、日本は各国と通商条約と交わし、政治的に、経済的に、西欧世界に組み込まれていましたが、この万国博覧会を通じて文化的にも西欧世界に組み込まれることを余儀なくされたのです。漆器や陶磁器や浮世絵など日本の美術品は西洋でいう美術であるかを評価され、美術工芸品、すなわち美術を応用した品々であり美術よりは一段劣るものという格付けをされました。それゆえ、日本国内では純粋美術をつくりだそうという動きが生まれました。美術が国家の体面、精華であると判断されたからです。1889年に開校された東京芸術大学は、西洋の教育制度を用いた日本美術の振興をはっきりと意図したもので、学校では油絵も洋風彫刻も教えず、日本画と木彫など在来の美術の教育から出発したことがこの学校の使命を良く物語っています。
明治の初期には日本画を描いた洋画家、洋画を描いた日本画家は数限りなくいましたが、明治20年ごろには「日本画」「洋画」という対置構図が出来あがりました。絵画はその文化圏的な出自を確認し「日本画」「洋画」のいずれかに帰属することになったのです。日本画家の洋行は大正時代に入るとしだいに増えてきますが、彼等は西洋絵画を学びつつも、融合ではなく、むしろ日本絵画の長所を強く意識し、近代の日本画をつくりあげていきました。洋画の分野では黒田清輝、藤島武ニ、原田直次郎などが洋画を日本に根付かせようと努力します。しかし彼らが最も悩んだのが油彩画という「技術」の習得を超えて、何をどのように描くかという表現内容でした。西洋芸術の流れのなかに身を置いたときに日本人が何を表現すべきか、この問題に対し、黒田清輝は「舞妓」や藤島武ニの「天平の面影」で日本古来の美を新しい技法で表現する道を選びました。西洋と日本の価値観が融合した新しい洋画は生まれなかったのです。
この洋画における芸術的な閉塞状況は岡本太郎が渡仏した昭和初期にも続いていました。この時代の芸術における状況は岡本太郎自身の言葉によって御説明した方が良いと思いますので、岡本太郎の「今日の芸術」から引用します。
日本でも明治時代に西洋画をはじめて取り入れ、型どおりの日本画とはガラリと違った新しい技法で、静物だの風景だのを描いたときの感動は十分分かります。またその後、黒田清輝などがはじめて裸体画を発表して問題となったのですが、それまで、いたずらに淫であり、不道徳であるとして卑しめられていた裸体画を芸術として押し出した、肉体開放のよろこびは察せられます。その自由と感動は芸術につながっているのです。しかし、今日ではもはや話がちがうのです。二十世紀の自由な精神は、さらに積極的に新しい課題にむかってつき進んでいます。この時代に、百年も前と同じようなことを、後生大事にくり返してみせているのでは、けっして芸術として人を打つことはできません。
当時は日本から留学に来ている絵かきたちも多かった。彼らはなんの疑いもなく、パリの街角を描いたり、ブロンドのモデルを雇ってきて裸にして、最新流行のスタイルでお尻をふくらまして描いてみたり、ひとのまねをすることそれが彼らにとってはまじめに勉強することなのですが、型をとり入れることだけにうき身をやつしています。それをもって日本に帰り、滞欧作品だといって披露すれば、当時では画壇的な地位もさだまり、万事おめでたかったのです。私にはそれができなかった。そんな絵をかこうとすれば、耐えがたい空虚感で、どうにもならなかった。生活を通しての必然性もないのに、形式的な、あるいはたんに感覚的なデフォルマシオン(変形)をやってみても何になるんだろう。
岡本太郎が感じたように、芸術はある文化、価値観、世界観のなかでうまれてきます。西洋のさまざまな価値観のなかで生まれた芸術を、その形だけをまねたところでその作品は本当の意味で芸術にはなれないのです。日本の画壇が日本画と洋画に分かれたのも、日本という文化のなかで評価される芸術と、世界と共通の土俵で評価する場合の芸術は違うものにならざるを得ないという理解があったからでしょう。
岡本太郎はこの時期、芸術についての迷いから一時制作活動をはなれ、パリのソルボンヌ大学で民族学などを学んでいます。
岡本太郎と抽象画
しかし、西欧を中心とする美術界ではこの時期より少し前に世界中の芸術を統一して新しい芸術を作ろうとする動きが出ていました。この時代の状況について岡本太郎の言葉を聞きましょう。
近代において、世界じゅうが西欧文化を受け入れました。しかし、同時に、逆にきわめて強力にヨーロッパ精神が、かって知らなかった異質のものによって動かされもしたのです。つまりヨーロッパの世界征服の結果、彼らをふくめて地球上のあらゆる文化圏がはげしく刺激しあい、交換され、東洋的でも西洋的でも何々的でもない、まったく新しい世界を生むにいたったのです。二十世紀はじめの革命的な芸術、立体派は、アフリカや南洋の黒人芸術から決定的な影響をうけていますし、野獣派や、さらにさかのぼってゴッホ、ゴーギャンなどの後期印象派は、十九世紀の終わりごろ、ヨーロッパでもてはやされた日本の浮世絵版画の影響をのぞいては考えることができません。このように、かって油絵はパリを中心としてのヨーロッパという、いわば小さな世界の中で、その中から、その環境内の人々だけをあいてにつくられたのですが、今日はその内容も、訴える相手も、世界的なのです。
日本画檀における芸術活動に違和感を覚え、また古典的な西欧芸術をそのまま受容することの出来なかった岡本太郎にとって、世界共通の芸術を創ろうとする動きは大変魅力的に見えました。岡本太郎の抽象絵画に関する言葉があります。
とにかく、私はここではじめて息がつけました。抽象画では自分をすこしもいつわったりする必要がありません。このままの自分を、その感動のままに、もっとも直截に、端的におしだすことが大事なのです。私のようなパリに住む外国人、つまりフランスの伝統とちがった世界で生まれ育ったものにとって、金髪美人やパリの風景を描く空しさ、ズレがないことだけでも、どんなに救いだったでしょう。
しかもこの形式は世界共通語として、だれでも語りかけることができる。純粋な線、リズム、色彩には、人と人とのへだてをつける地方色というものはありません。パリの街角やまた、それが富士山ならば、その土地の人間と外国人とでは、対し方、それによってひきおこされる感動はまるで違うでしょう。よかれあしかれ、そのモチーフには民族の生きてきた歴史、伝統がおわされているのです。そういう地方的(ローカル)な匂いや約束ごとは、すっぱりと切り捨てている。したがって、それに、ほんとうに親しめる、親しめないとか、理解できる、できないという、地理的、民族的なずれもありません。
日本人としてパリの真ん中でやっていく場合、ローカルカラーなどで割引きされる、また逆に買いかぶられる心配もなく、まったく対等に、共通の課題をもって、直接的に参加できる。これこそほんとうに世界的な表現形式であると感じとったのです。
岡本太郎にとって、共通の課題をもって参加できる芸術活動を得ることができたことは本当に幸せなことでした。この新しい芸術の世界で太郎は才能を発揮し、初期の名作を制作しますが、岡本太郎はここでも本当の意味で世界芸術を発見できたわけではありません。岡本太郎のこの時期の名作といわれる「傷ましき腕」や「空間」などの系列はピカソなどの当時圧倒的だった荒っぽいバーバリズムに対して、むしろ日本的な叙情的な要素を抵抗として押し出したものであり、日本の美を抽象画の手法で表現したものでした。太郎はここで第二次世界大戦にまきこまれ、日本に帰国、徴兵され数年を軍隊で過ごすことになります。
敗戦後の日本で本格的に制作を開始した岡本は、新しい時代を迎えたはずの日本が、相変わらず古くからの伝統や権威にしばられている状況に直面しました。人々が当たり前と思っている美の規範をいったん覆さなければ自由な創造活動は不可能であると感じた岡本は、日本の美術界に徹底的な異議申立てを行いました。戦後の日本には過去の日本芸術を支えた、例えば宗教的価値や、宮廷文化、禅宗文化、武家文化、町人文化はすでに存在しませんでした。そのため、過去の日本の芸術の伝統を追っても、それは懐古趣味ではあっても、新しい芸術、価値観の創造にはつながらない、と岡本太郎が感じても無理はありませんでした。私は岡本太郎に100%同調するわけではありませんが、彼の日本画に対する厳しい批判を紹介します。
今日の日本画は、明治の初期、西洋崇拝に対する反動として国粋主義的な意味で確立されたものだが、それを意識しすぎて、形式的に伝統にとらわれ、また別の面では西洋の写実主義の影響もあり、却ってアブハチとらずの非芸術に堕してしまった。----日本画も----日本舞踊でさえ---(この目の前の生きている芸者の)微妙な動態美にくらべると、まるで死んだ形式美のように思えて来たのである。
岡本太郎の「夜明け」や「重工業」、「森の掟」などの作品は単に美術界に対してだけではなく、日本社会そのものへの批判としてとらえられ、大きな波紋をよびました。このような社会的な注目のなかで、岡本太郎は、戦後期ともに活動した画家たち同様に、激動する社会の現実を前にして悩んでいました。批判を超え、どのような価値観を社会に対して打ち出すのか、芸術に社会を導くというかってない役割が期待される中で、岡本太郎の苦悩には深いものがありました。
縄文の発見
1951年(昭和26年)の秋、偶然、東京国立博物館の考古学資料のケースの隅に、石器や骨角器と同列にならべられた縄文土器を見つけた時、岡本太郎は電撃に打たれました。
私の血の中に力がふき起るのを覚えた。豁然と新しい伝統への視野がひらけ、我国の土壌の中にも掘り下げるべき文化の層が深みにひそんでいることを知ったのである。民族に対してのみではない。人間性への根源的な感動であり、信頼感であった。
縄文文化は岡本太郎の価値の発見に至るまで、美術的価値はおろか、文化的価値をみとめられていませんでした。現代の教科書の日本文化のトップに縄文土器の写真がとりあげられるようになったのは、岡本太郎の、縄文土器の価値の発見があったからです。岡本太郎が縄文土器を取り上げたのは、ナショナリズムでも懐古趣味でも、またエキゾチックなプリミチーブ愛好でもなく、縄文土器が日本の風土、土壌に根ざした、まさに根源の文化であると感じたからでした。彼が発見したのは、縄文土器の形態や、紋様の話ではなく、そこに噴出している縄文人の、純粋で、分厚い生命力だったのです。
岡本太郎は芸術の本質を「超自然的激越」と捉えていました。これをもう少し分かりやすい言葉でいうと、「非常に力強く噴出してくるもの」、もっと分かりやすくいうと、「いきいきと涌き出てくるもの、生命力、躍動美」ということになります。縄文芸術の存在は、岡本太郎の芸術に対する考えが誤りでなかったことの確かな証拠となり、縄文の発見後、岡本太郎の作品はさらに生命力、躍動美を増したように見えます。
岡本太郎は西洋から移入されてきた芸術の価値観と、日本人であるという歴史や情念を背負い込んだ日本芸術の価値観との間の矛盾を、芸術の本質を生命力、躍動美と位置付けることによって克服したのです。この生命力・躍動美という美は、彼が探し求めていた、一つの国、伝統にとらわれない、世界の人が、芸術家がともに親しみ、追求できる芸術の価値でした。
岡本太郎はこの時期以降彫刻の作品を数多く制作するようになりました。それは生命力・躍動美という彼の芸術の本質をより多くの人に分かりやすく表現できるものだったからでしょう。ここで彼の作品を見てみましょう。
大阪万博と岡本太郎
日本が開国して以来、万国博覧会は世界に日本を紹介するための最も重要な機会であり、実は戦前から、日本に万国博覧会を誘致しようとする動きはたびたびありました。それが、急速に実現に向かったのが、1964年の臨時閣議における万国博覧会条約批准であり、65年のパリの博覧会国際事務局による開催承認からでした。万博は開催にむけて、東京では東京都庁舎・代々木屋内競技場で岡本太郎とともに活躍した丹下健三が、大阪では岡本太郎とパリ時代から親交のあった桑原武夫や小松左京、梅原忠夫が活動していましたが、1967年に万博協会からの強い要請を受け、岡本太郎が、テーマプロデューサーを引き受けました。
岡本太郎は万国博覧会のテーマ館として太陽の塔を構想し、太陽の塔の地下に過去を、太陽の塔内部には生命の樹をそびえさせ、そして塔を通って登っていく空中、丹下健三の設計したお祭り広場にかかる大屋根の中に未来を展示するプランを作りました。過去の展示には、宇宙の大爆発から、生命の誕生、DNAなど神秘的な生物の発生と分化、さらには宗教の発生を、現在の展示には、世界中のいま生きている民衆、老若男女のいきいきとした表情を、未来には最新の情報システムや都市工学による未来都市の提案など、時間と空間を超えた有機体としての世界を表現しました。
ここからは岡本敏子氏の著書、「岡本太郎に乾杯」を引用します。
彼はテーマプロデューサーに就任したその時から、「オレはテーマの"進歩と調和"には反対だ」と公言してはばからなかった。「人類は進歩なんかしていない。なにが進歩だ。縄文土器の凄さをみろ。ラスコーの壁画だって、ツタンカーメンだって、いまの人間にあんなものが作れるか。"調和"と言うが、みんなが少しずつ自分を殺して、頭を下げあって、こっちも六分、相手も六分どおり。それで馴れ合っている調和なんて卑しい。ガンガンとフェアーに相手とぶつかりあって、闘って、そこに生まれるのが本当の調和なんだ。まずたたかわなければ調和は生まれない。だから《太陽の塔》なんだ。EXPO′70=進歩と調和だという訳で、テクノロジーを駆使し、ピカピカチャカチャカ。モダニズムが会場にあふれることは目に見えている。それに対して、ガツーンとまったく反対のもの、太古の昔から、どんとそこに生えていたんじゃないかと思われるような、そして周囲とまったく調和しない、そういうものを突きつける必要があったんだ」
体の中に、過去と現在と未来を宿すもの、それは生命体そのものなのかもしれません。太陽の塔は、モダニズム、科学文明至上主義に対するアンチテーゼとして、古代からつながる、おそらくは縄文人がもっていたような、生命の力、さらには自然との共生を象徴しているように思われます。小松左京氏の岡本太郎の著作に贈った言葉があります。
万国博自体には、近代産業文明の成果の展示、といったモメントを、一つの伝統としてふくんでおり、EXPO′70でも、初期には、それで一元化してしまおうという動きもあった。しかし、一方では、第二次大戦後に続々と独立してきた諸地域民族の「文化のフェスティバル」としての性格が、特に戦後はつよくなりはじめ、日本万国博では、前回モントリオール博にもまして、その点が強調される事になった。 -------------- ところが、岡本さんの「太陽の塔」は、その象徴性において、産業社会も、インターナショナリズムも、いともあっさり「超えて」しまっているのである。一方からは、近代的国家分割以前の「過去」「原始」の生命力をくみあげ、それを上方の「産業技術文明」をつきやぶってふき上げる事によって。
この日本万国博覧会は、日本にとって、1867年のパリ万博以来初めて、日本を西欧社会と対等な文化の担い手として世界にアピールできる場でした。万博のほとんどのパビリオンは、すべての先進国が当時共通に経験していたモダニズム、科学万能主義の精神によって設計、建設されました。しかし、岡本太郎は科学万能主義もやがて移ろい行くものだということを見ぬき、もっと人間存在に根源的なもの、生命力、自然との共生を大阪万博のテーマの中に取りこんだのです。この精神は、意識する、しないにかかわらず、大阪万博を訪れたひとびとに腹のそこで認識され、万博に深みを与えたのでした。
この万博により、それまで西欧世界から疎外されていると感じていた日本人も、自らが世界に対等の存在として認知されているという思いを持ちました。その後の経済的成功もあいまって、日本社会に存在していた西欧と、日本の対立という問題意識も解消されていったのです。実はそれゆえに、私はこの時から90年代後半、社会が再び岡本太郎を必要とするまで、西洋と日本の精神の対立を基軸として行われてきた岡本太郎の活動は、芸術としての意味をもちつつも、社会的な注目を失っていったと感じています。
現代日本における岡本太郎の意義
いま千里丘陵に行き、太陽の塔を見上げると、それは実に力づよく、しかしとても淋しくそこに立っています。太陽の塔は、西洋文明に対して日本の知性が力をあわせて発信した新たな文化と芸術のパラダイムでした。しかしその存在の意味を、日本の次の世代の知性は受け継いでいっているとは思えないのです。日本人が、本当に生命力、自然との共生という理念をしっかりと受け止めていたなら、1970年から30年たった今、日本人がバブルの崩壊、物質至上主義の終焉、西欧文明、特にアメリカ文明への精神的敗北感で右往左往することはなかったでしょう。
科学文明、物質文明が万能でないことは、岡本太郎はとっくに見抜いていました。また西洋文明・アメリカ文明に対しては民族学者の泉靖一氏との対談のなかでこのような発言をしています。
(西欧文明は)経済、あるいは力の面ではたしかに世界を圧したが、だからといって、芸術とか文化の中心がニューヨーク、ロンドン、パリであるという必然性はない。(中略)メキシコ人にいわせると、気楽に「アメリカは金持ちだ。しかし文化はわれわれの方が上だ」といってのける。日本人で、そんなことをいうやつはいないですよ、お金持ちや成功者はみんな偉くて、人格高潔で、文化的にも高いと、はじめから頭を下げてしまう。
もうひとつの問題はいま世界がジェネラライズ(一般化)されているということです。日本でみる光景も、ニューヨークやバンコクもそれほど変わりがない。日本で使われている自動車、機械、テレビ、生活用具一般、建築物、世界中のそれら、考え方やモラルのすべてが一般化されているわけだが、その虚しさをようやく感じつつあるのではないか。あるいはまだ感じていないかもしれないが、いずれ近いうちに感じるだろう。(中略)画一化する世界に対して、いかにわれわれは独自な人間的な創造的ないろどりをぶつけていくか、つまり、この時点においてどのくらいわれわれが純粋に生きて人間としての生きがいを示すかということが問題だと思うのです。ニューヨークでもパリでも南アフリカでも、同じような変哲もない現代のパターンに従って生きるということが、はたして生きがいであるかどうかということを確かめてみなければならない。と同時に、かっての人間の生き方を検討し、日本においてもアフリカ、東南アジア、あらゆる地域で、互いに響き合わせ、もういっぺん理性的、情熱的、本能的に生きがいというものを再確認する必要があるのではないか。
これに対して泉 靖一氏はこのように答えています。
ぼくは、その意味で、御意見に全く賛成なんです。ただ、近代社会の一般的、普遍的な文化というものは、一体普遍的なんだろうかという疑問があります。ぼくは、西ヨーロッパ主義というものは非常に極限されたところから発して、それが力やその他のいろいろな関係で、パーッと広がったのだと考えています。それはある意味では人間性を疎外するような特殊な文化であるにもかかわらず、一般化したということに非常な矛盾があるのです。むしろ、非常に創造性のある、しかも伝統的な文化の中にこそ、本当の人間性の開放があるのではないだろうか。そういうものの中に、伝統のうるわしさなり、日本という列島の中の文化の歴史があったのではないかと思うのです。
私は、これらの言葉の中に、今日我々が議論しなくてはならないことの答えがもう出ているように思います。いたずらに西洋文明をおそれることなく、劣等感をもつことなく、どれだけ日本人らしく生きて、自らの生きがいを見出すかが大事なのだということです。西洋の価値観のなかで、いかに自らが評価されるかが大事なのではない。自らの文化を楽しみ、人間性を開花させることが大切であるということを、いま我々は胸にきざまなくてはなりません。
岡本太郎が現代において価値があるのは、岡本太郎の芸術が、そのまま哲学であり、いままさに日本の進むべき方向を指し示しているからに他なりません。
(仮称)太陽の塔美術館構想について
ここまで述べてきた、現代日本における岡本太郎芸術の重要性を考えるとき、一般の人々が、その場所を訪れることにより自然とその哲学と芸術を感じることの出来る美術館をつくる必要があると思います。またその場所は太陽の塔のすぐ傍であるべきです。川崎市の岡本太郎美術館は、岡本太郎・一平・かな子の芸術の全体像を示そうとするあまり、現代日本にむけてのメッセージ性がやや希薄になっていると思われます。また場所が太陽の塔と離れているのが最大の問題であり、岡本太郎氏の作品を中心とした二つ目の美術館が必要な所以であります。
この美術館をここでは仮に太陽の塔美術館と呼ばせていただき、検討の現状について簡単に御説明いたします
万博公園内に国立国際美術館があるのを皆さんは御存知だと思います。この国立国際美術館は文化庁の施設等機関として設置された4つの国立美術館のうちの一つです。まず、ここで、日本の国立美術館が4つしかないことを見ても、岡本太郎作品のための美術館が国立で建設されることはまずないと考えるべきでしょう。
ところがこの国立国際美術館は新館が大阪市内中之島の市立科学館どなりに建設されることになっており、2003年以降の万博公園内の建物については利用予定がないのです。そこでこの建物を利用して美術館ができないか、という考えがでてまいります。
ところが問題になるのがお金です。バブル期にならともかく、現在お金をだせる企業はほとんどありませんし、また御存知のように吹田市の財政状況も他の多くの自治体と同じく大変厳しい状況です。人件費のカットや、福祉や補助金の見なおしを行っているなかで、文化に多くのお金を投入するのは、市としてなかなか出来ることではありません。また、万博協会は現在主に万博公園の管理業務を行っており、吹田市が動かない限り、率先して新たな企画や投資を行って下さることはまずないのではないでしょうか。
阪口市長は岡本太郎の価値についてはよく認識してくださっていますが、最終的にはお金の問題があり、この事業が前にすすまないというのが現状です。しかし、私は太陽の塔美術館にお金を使うことが市民の税金を無駄にすることになるとは決して思いません。いやそれどころか、現時点で岡本太郎の作品を収集することは市民の税金を最大限に生かすことになると思います。
市の経営という観点から申しますと、少子化や産業の縮小が進むなかで、今後は各自治体が、住民や企業を奪い合うような時代がやってきます。市民や企業がどの都市に住むかを厳しく選択する時代がくるのです。そのために、吹田市を他市とどのように差別化するかが大事になります。吹田市が、岡本太郎の芸術を理念の一つとしてまちづくりをすることは、それだけで他市との差別化になるのです。
今日講演会に参加していただいた皆さんが、岡本太郎氏の作品について興味をもちつづけてくださることが吹田市が美術館設置の決心をする力となります。ぜひとも皆さまの一人一人が吹田市に対し声を上げていっていただきたいとお願いし、岡本太郎の芸術、吹田市にとっての重要性のご説明とさせていただきます。本日はご参加まことにありがとうございました。
太陽の塔美術館を求める市民の会
文責 山口克也