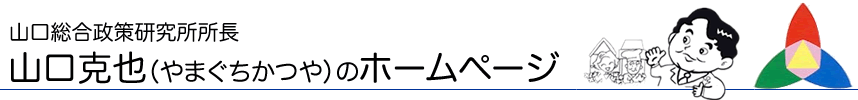第二章 社会保障の今後
社会保障が経済に占める規模
少子化問題が起き、社会の高齢者の割合が増えてくると、すぐに維持が難しくなってくるのが社会保障システムです。現在日本の社会保障費はどのくらいの規模になっているのかをまず2013年の財務省資料を使って見てみます。「社会保障関係費」の規模は29.1兆円で、総額92.6兆円の一般会計予算のうち31.4%になっています。次いで大きいのが国債費の22.2兆円、地方交付税交付金等が16.5兆円と、この2つは国が支出額を決められない歳出であり、一般歳出(全体からこの2つを除いた残り)に占める社会保障関係費の割合は54%にも達します。公共事業費が5.3兆円、文教及び科学振興費が5.4兆円、防衛費が4.8兆円であることと比較すると、非常に大きな金額です。
ところが、一般会計に現れる「社会保障関係費」は日本の社会保障費の一部でしかないのです。年金にせよ、医療保険にせよ、介護保険にせよ、雇用保険にせよ、日本の社会保障制度の根幹は「社会保険」、つまり保険料をとって、その中で給付を行う制度になっています。保険料収入は国の一般会計に入る財源ではなく、特別会計や地方会計、個別の保険制度の会計に入って支出されるものですから、一般会計に現れる「社会保障関係費」とは関係ありません。それでは、保険料で賄われている分も含めて、社会保障給付にかかっている全費用「社会保障給付費」は現在110.6兆円(平成25年(2013年)予算ベース)という規模に達しており、これに、医療や介護で国民が自己負担で支払っている分を足すと、だいたい国民総生産(GDP)の4分の1程度、130兆円近くが社会保障に使われていることになります。
そして、この社会保障費は、少子高齢化の中で急速に増加しているのです。税金と保険料で賄われている社会保障給付費の合計は、2013年度予算ベースで110.6兆円ですが、これは過去5年の平均で毎年3.44兆円増えています。国立社会保障・人口問題研究所の予想では、2025年にこの数字は2013年と比較して30兆円増え、140兆円に達すると予想されています。学習院大学経済学部の鈴木亘教授によると、厚生労働省が2025年までについて予測している方法を使って少子高齢化を前提にその先までの社会保障給付費の計算を行うと、2025年度の148.9兆円が、2035年には189.6兆円、2050年には257.1兆円、2075年には340.9兆円まで増加し、2025年、2035年、2050年の国民所得に対する比率は、それぞれ、2013年度の30.8%から大きく増加し、39.9%、47.3%、62.4%に至り、2050年度の国民負担率(社会保障の保険料負担や消費税などの税負担が国民所得に占める割合)は71.6%に達し、その時の勤労者は、想像を絶する保険料に加えて50%以上の消費税を支払うことになる、と試算されています。凄まじい社会保障給付費の増加は、その反面として、その時働いている勤労者が保険料や税金で負担していかなくてはならないものであり、その支払い金額は、政府が現在の年金などの社会保障制度の中で、約束してしまっているもの、すなわちすでに発生した、その人たちの債務だというのです。
社会保障における財政悪化の原因
日本の社会保障はなぜこれほど深刻な財政問題を抱えるに至ったのでしょうか。鈴木亘氏は、諸悪の根源は、世界最速の少子高齢化が進む状況下にあってもなお、「賦課方式」という不適切な財政方式を、惰性的に続けていることにあるといいます。賦課方式というのは、高齢者世代が受けとっている年金、医療、その他の福祉サービスにかかる費用を、主に今の現役層が支えるという財政方式のことです。そして、高齢者が多くなり、現役世代が少なくなっても過去に約束した福祉サービスを切り下げることをしていないのです。日本の年金制度は、設立当初からしばらくの間は、「積立方式」として、自分が将来に受け取る年金受益額に見合うだけの保険料を納める仕組みでしたが、1970年代初めから、なし崩し的に現在の「賦課方式」に移行してゆきました。すなわち、高齢者の年金額を増やすために積立金からの大盤振る舞いをはじめ、保険料も受益に見合うだけの徴収を怠ってきたのです。例えば、2014年1月現在の厚生年金保険料率は17.1%にもなりますが、1970年にはわずか4.6%にすぎませんでした。2009年に厚生労働省が試算したところ。厚生年金と国民年金を合わせた年金純債務は、積立金が150兆円あるものの債務が950兆円あり、800兆円に達していることが分かっています。これに厚生労働省が管轄していない共済年金の分を加えると、総額およそ900兆円程度になると思われます。鈴木氏によれば、純債務額は年金のほかに、医療保険で380兆円、介護保険で230兆円あり、社会保障全体の純債務額は約1500兆円存在します。
これほどの純債務が生じているということを、国民一人ひとりに落とし込み、世代間不公平がどの程度のものなのか、見ることにしましょう。個人の雇用状況、家族状況によって、社会保障による損得は大きく変わりますが、ここでは社会保障からより利益を受ける、専業主婦の配偶者のいるケースで考えます。(保険料率などの前提は、鈴木亘 「社会保障亡国論」p63をご参照ください)そうすると、1940年生まれの人は年金、医療、介護の全体で4,930万円生涯で得をすることになりますが、1965年生まれの人は、差し引きトントン、1970年生まれ以降の人は損となり、2000年生まれの人で3,240万円のマイナス、2010年生まれの人で3,650万円のマイナスになります。すなわち、2010年に生まれた人は、一人あたり3,650万円の借金を背負って生まれてくることになります。これは一種の「幼児虐待」というべきではないでしょうか。しかし、家族の中では絶対に行わないような非人道的行為を、日本の社会保障制度は国民に強いているのです。
しかし、これほど大変なことが、どのようにして国民に隠されてきたのでしょうか?年金は「100年安心プラン」によって、中長期的財政均衡が保たれていたのではなかったのでしょうか?実は厚生労働省が発表した統計数値そのものに問題があったのです。
厚生省が2009年2月に発表した、5年に一度年金財政の健全性をチェックするための「財政検証」では、リーマン・ショックが起きている最中であるにもかかわらず、なんとリーマン・ショック前の景気好調時の統計数値が用いられていました。そして、今後100年近くにわたって運用利回りを年率4.1%という高利回りに設定し、賃金も年率2.5%で100年近く上昇することが前提になっています。さらに、当時も4割程度であった国民年金保険料の未納率が、2009年度中に2割に急減するという希望的想定になっているなど、まさに「粉飾決算」としか言いようがない代物です。その後日本経済はリーマン・ショックによる景気急落に見舞われ、2011年には東日本大震災、その後のデフレと2009年の財政検証で想定していたバラ色の経済状況からは全くかけ離れた「想定外」の状況が続いており、年金財政の健全性など、どこにも存在しない状況になりました。
制度改革の可能性
このような状況下で、政府は社会保障制度におけるもっとも重要な施策として、消費税率の引き上げを行いました。消費税率の引き上げとそのスケジュールは、民主党政権下で進められてきた「社会保障と税の一体改革」で議論され、当時野党であった自民党、公明党も含めた政策協調(3党合意)を経て、2012年8月の「一体改革関連法案」の成立とともに決定されたものです。安倍政権はこれを踏まえて2014年4月に消費税を5%から8%に引き上げましたが、消費の減退を招き、経済に悪影響を与えました。消費税を10%に引き上げるところまでは決定されているのですが、この後の現実の政治過程の中で、なかなか引きあげが行われていません。
消費税引き上げと並んで、今後の社会保障改革を考える上で重要な要素となるのは、2013年8月に公表された、「社会保障制度改革国民会議」の報告書です。今後の社会保障制度改革についての基本的な考え方を示したもので、①高齢者を特別あつかいしない②社会保険への安易な税金の投入をしない③将来世代への負担先送りを速やかに解消、などという、それまでの政府の報告書になかった、鈴木氏によれば「正しい」方針が示されています。しかしながら、精神論はよくても、実際の報告書の具体論ではあまりめぼしいものは見られません。
それでは、厳しい状況にある社会保障制度を改革する方法はないのでしょうか?改革の方向性として、すべての「数学的な」可能性を挙げるとすると、消費税などの税金の投入、保険料の引き上げ、支給年齢の引き上げ、給付の引き下げがあります。それぞれについて考えてみましょう。
消費税の引き上げによる対応の問題点は、若者に厳しく、高齢者に手厚い日本の社会保障制度における「歪んだ所得再分配」をさらに強化してしまうところにあります。日本の社会保障制度の根幹は、「社会保険方式」にあります。すなわち、給付は保険料の中から行うというものです。現在、基礎年金、介護保険、高齢者医療の半分は税金と借金で賄われている状況です。このような税の投入は、社会保険方式を採っている国々ではほとんどあり得ない規模に達しています。わかりやすくいうと、非常に高額の所得者に対しても、医療費の半分、介護費の半分、基礎年金の半分を、勤労世帯や将来世代が負担するということになるのです。このような方向性を強化していいはずがありません。保険料の引き上げはこれまで何十年にわたって繰り返されてきた年金改革の定番ですが、現役層のみへの負担増であり、若者への負担が増大し、少子高齢化をさらにもたらしてしまうという問題があります。
それでは、年金の支給開始年齢の引き上げはどうでしょうか?現在、年金は支給開始年齢を60歳から65歳まで引き上げている最中であり、その完了には少なくても2025年度まで待たなくてはなりません。引き上げペースを現在の3年に一歳というペースから二年に一歳というペースにするということも理論的には考えられますが、企業の退職年齢引き上げとの兼ね合いもあり、スケジュールの変更は政治的に困難であると思われます。それでは年金の支給開始年齢を65歳からさらに
引き上げていく場合、最終的に何歳まで引き上げなければならないのでしょうか。
厚生年金について鈴木氏の行った試算があります。現在の状況では、積立金は2038年に積立金が枯渇する予想です。改革手段を支給開始年齢引き上げのみに限定して、三年に一歳ごとの現在の引き上げのペースを維持し、70歳まで引き上げた場合、2054年まで積立金が持つことになります。100年安心プランの財政状況まで戻そうとすると、75.5歳まで支給開始年齢を引き上げなくてはなりません。これも、積立金の運用利回りを2.5%、賃金上昇率を2%、物価上昇率を1%とした、楽観的な計算なのです。これで、2011年現在の、基礎年金6万5741円、厚生年金受給者の平均年金受給月額16万3254円と同等の金額の支給ができるというのです。支給開始年齢を65歳から70歳に引き上げることによる給付減は1374万円であり、75.5歳まで引き上げる時の給付減は2885.3万円です。政府は国民に、この年になるまで働きつづけ、賃金でなんとかしろ、というのですが、高齢者が安い賃金で働くと、それは若者の仕事を奪うことにもなりかねず、少子高齢化はさらに進行することになります。また、いくら最近の高齢者は元気になったとはいえ、75歳まで壮齢者と同等の仕事をすることは難しいのではないでしょうか。
最後に給付の引き下げについてコメントしておきます。現金給付される年金や、雇用保険については、いままでに述べた状況の下では金額の多寡を述べられるような状況ではありません。それ以外の社会保険分野については、医療、介護、保育等の分野において実際にサービスが現物支給されていますので、その現物支給が適切かどうか、ということが問題になります。これも鈴木氏の言葉になりますが、日本の社会保障産業は、その供給の効率性がとても低く、給付効率化の余地はとても大きいのです。その理由は、過剰な参入規制、価格規制が行われていることによって、この分野に競争原理がほとんど働いていないからです。安易かつ多額に投入されている公費・補助金の存在が高コスト構造を生み出し、さらには高コスト体質が社会保障産業の各分野に強大な業界団体や労働組合を組織させる原資となり、政治活動を活発化させる要因になっています。このように社会保障産業は、政治家、官僚機構、業界団体と結びつき、「安定的構造」を形成しており、しばしば「岩盤規制」と言われるように、改革の実現が極めて困難な領域をこの分野に作り出しています。
ここまで目を背けたくなるような社会保障分野の現実を見てきました。少子高齢化によって生じた社会保障分野の困窮は、さらに若者世代への圧力として降りかかり、少子化を進める可能性があります。いかにこの社会保障の問題から若者世代を守るか、というのがこの本の取り組むべき課題となります。この後に行うバックキャスティングのなかで、その方法は姿を現すはずです。そのバックキャスティングに必要な情報を集めるため、次の章では、少子高齢化をもたらした東京一極集中問題、そして東京一極集中の反面であり、少子高齢化がもたらすもう一つの課題である、地方消滅の問題について現状把握を行うことにします。