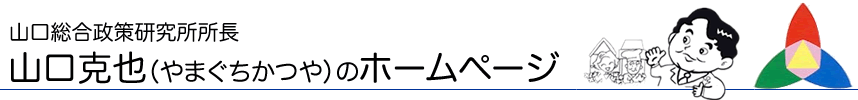◆ 進化論について(2009年2月27日)
日経サイエンス2009年4月号では、「種の起源」から150年ということで“進化する進化論”という特集が組まれている。進化論の歴史、変遷が書かれていたのだが、この歴史の中で、木村資生の「分子進化の中立論」、今西錦司の「棲み分け理論」がほとんど取り上げられていなかったのは、いただけない。なぜなら、この両理論は、進化論に潜在する、社会進化論に通じる思想的危険性を緩和する、重要な役割を果たしているからだ。
生命が、「突然変異」と「自然選択」によって進化していくというのが、ダーウィンの進化論の基本理論であり、この理論は20世紀前半、メンデルの遺伝の法則と統合され、理論基盤が確立、1953年にDNAの二重らせん構造が発見され、分子レベルでの進化研究がおこなわれるようになった。
進化論の第二の進化ともいわれるものが、木村資生による「分子進化の中立性」の提唱で 生物の進化を分子レベルで見ると、自然選択によって起こるDNAの変化はいわば「少数派」であり、ほとんどは、生き残りに有利でも、不利でもない、いわば中立的な変化であるとされたのである。この雑誌に“自然選択の重要性”を強調する趣旨で書かれた、ある論文にも、
研究対象になったショウジョウバエの6000個の遺伝子のうち、自然選択が働いて残ったものが、五分の一、あとの五分の四は自然選択によらない遺伝的浮動によるものだ、という報告がなされている。
分子進化の中立性から導き出される、論理的な帰結は、生物の群れは、同じ環境のもとでも自然に変化し、多様性を持っていくということである。そして、重要なのは、多様性は、群れを構成する構成員の間に蓄積するだけでなく、群れと群れの間にも蓄積していくということだ。
従来の進化論において、「自然選択」されるのは、個体であると考えられていた。群れの中に、特定の環境に適応力を持つ個体が突然変異によって生まれ、それが沢山の子孫を持つことによって自然選択されていく、という状況も、ありえなくはないだろう。
しかしながら、よりあり得るのは、環境変化の場において、それまである地域で中心的な役割を果たしていたグルーブが衰退し、それまでの環境の下では“中立的な”進化により別の個性を獲得していたグループが移動してきて、代わりに中心的な役割を果たすことになるという状況ではなかろうか。
今西錦司は、進化論的な観点からは、「進化における生物の主体性」という観念を用いるなど、問題も多いと思うが、生態学者としての視点から、ある地域における、生物種の変化が、個体ではなく種という単位で起こり、より広い地域をみると、類縁関根にある、さまざまな種が棲み分けをしている、という発見をし、このような事態が、個体の変異と、自然選択という考えでは説明できないのではないか、という問題提起をしたことが、非常に重要であると思う。
今西錦司のいう、現実の自然界における、特定地域における種の変遷は、「分子進化における中立性」からもたらされる「多様性の蓄積」と「移動」という観念によって、明確に説明可能だ。
すなわち、ダーウィンの唱えた、「突然変異」と「自然選択」というキーワードに、木村、今西理論は、「多様化」と「棲み分け」という観念を付け加えていると思う。
特定の環境とはなれて、絶対的に優れた種など、これまで自然界には存在しなかった。 この地球上には、これからもさまざまな個性をもった色々な生命が共生し、棲み分けを していかなくてはならない。だからこそ、進化を語る時、木村資生と、今西錦司という二人の日本人科学者の名前を大切にしなくてはならないと考えるのだが、どうだろうか。