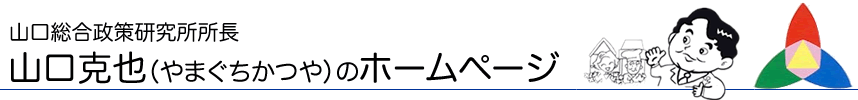第一章 少子高齢化は日本社会を破壊する
少子高齢化のもたらす問題
少子高齢化が日本社会を蝕んでいることは、多くの人に理解されるようになりました。しかしながら、「地球は人口爆発で、大変な状況じゃない?」とか、「日本は国土が狭く資源もないんだから、人口が少々減ったほうがいいんじゃない?」という疑問は当然出てくるだろうと思います。そこでまず最初に、少子高齢化がなぜいけないのか、どのような問題を社会にもたらすのかについて述べたいと思います。
まず、生命としての人間がこの40億年行ってきた営みに思いを馳せなくてはなりません。地球は、巨大隕石の衝突、マントルプルームによる巨大火山の連続爆発、メタンハイドレートの崩壊などによる、大変な環境変動を経験してきました。私たちの祖先である当時の生命は、さまざまに姿をかえながら厳しい環境に適応し、命をつないできました。すべての生命には生きようとする傾向があり、いや生きたい、生命をつなぎたいという思いがあり、それがこの地球を生命にあふれた美しい場所にしているのです。人間の一人もいない世界を私たちは美しいと感じられないでしょう。美しい田園風景も、街の形も、そして森林でさえ、人間が手を加えてその美しさを保っているのです。我々人間にとっても、生命をつなぐことが最も重要な役割であることは論を待ちません。子供を持つことは、男女が協力して、新しい生命を産み育て、未来へ命をつないでいく大切な行為です。そして、少子化は、この生命・人間の再生産の過程がうまく機能していないことを意味します。
少子化は、大きな社会的問題を引き起こします。直接的には「人口構成の変化」「高齢者割合の増加」が起こります。それによって社会には「労働力不足」、年金などの「社会保障負担の増大」、そして「経済成長の鈍化」などのデメリットが生じます。また、少子化は、「地域格差」「家族格差」を伴って進行します。少子高齢化した地域からは労働力のみならず、購買力・需要も消滅し、さまざまなサービス業が撤退します。そして人間の居住地域が減少、地域消滅が起こります。次に起こるのは家族格差です。多くの若者が、結婚して子どもを持つことを望んでいながら配偶者や子どもを持つことができない状況が起こっているのです。若者の四分の一が結婚せず、4割は子どもを持つことができていません。この数字だけからでも、いかに多くの若者が、引き裂かれるような悩み、苦しみの中にいるかが想像できます。
地球が人口爆発の中にあるのではないか、という疑問に対しては、国連が毎年出している「世界人口白書」の予想が答えを与えてくれます。あくまでも発展途上国等における家族計画やリプロダクティブヘルスに必要な投資が行われるという前提ですが、地球人口は2050年に97億人、2100年に112億人程度で横ばいとなる見込みです。そして、現在からの増加を後押ししているのは、寿命の伸びなのです。世界の女性一人当たりの出生率は、現在の2.5人から21世紀の末には平均2人に低下すると国連は予想しています。さらにいうと、1979年の世界人口白書のテーマは「人口増加のスローダウン」でしたし、1980年は「世界中で出生率の低下」、1982年は「人口における成功」でした。人口爆発の抑制には20世紀末にすでに目途が立っており、21世紀中に人口は安定するのです。バリ協定などによる再エネへの転換が行われると地球温暖化は食い止められ、食料問題、資源問題も潤沢な再エネ供給により解決する可能性が高いのです。地球温暖化対策に成功すれば、世界の未来は明るく、21世紀において、日本が少子化に向かう必然性は存在しません。
少子化が起こっても海外から移民をいれてくればそれで済む、という人がいたら、その人に聞いてみてください。「あなたは、私や、私の子どもたちが、地球上からいなくなっても、それでいいというのですか?」と。
日本の少子化問題と今後
日本における出生数の推移を振り返りましょう。
1945年から50年は、戦後のベビーブームです。1949年には269万6638人が生まれていました。1950年から1955年にかけては、国が豊かになり、死亡率が減少することで、歴史的な必然として出生率は年間200万人から160万人まで減少します。その後、1955年から1975年にかけては、1973年に209万2000人という第二次ベビーブームのピークがあったものの、結婚や出産は安定していました。1973年における合計特殊出生率は2.14です。
1972年ローマクラブが「成長の限界」を発表した後、世界的に人口を抑制しようとする動きがありました。日本も率先して出生率を抑制しようと、「子どもは二人まで」という合意をつくりあげていました。1989年、平成元年における合計特殊出生率は、1.57まで減少しています。出生数は1993年には120万人を切り、第二次ベビーブーム世代が出産適齢期を迎えても増えることなく横ばいとなりました。2005年には合計特殊出生率が1.26となり、出生数も110万人を割り込みました。出生率が先進国で最低レベルになり、出生数も30年で半減したのです。
2005年の国勢調査では未婚率、つまり一度も結婚していない人の割合が急上昇しています。ちなみに、30~34歳までの人のうち、未婚者は男性47.1%、女性32%に達しています。結婚した女性が産んだ子どもの数(夫婦出生率)も、2002年までは2.2前後で安定していましたが、2005年には2.09に下がりました。
それでは、今後日本の出生率や人口、人口構成はどうなっていくのでしょうか?国立社会保障・人口問題研究所(社人研)は、公的年金の財政見通しなどのために、日本の将来人口の推定を行っています。社人研が平成29年に行った推計によると、合計特殊出生率は今後50年1.44で推移すると予想され、日本の人口は2060年には9284万人、2110年には5343万人になる見通しです。社会保障給付の見通しを立てる上で重要となる65歳以上人口比率は、2025年に30%を超え、2040年には35%、2050年代には約38%となり、それ以降は同水準で推移します。医療や介護の一人当たり費用がより多くかかる75歳以上の人口比率は、2015年に12.8%であったのが、2026年には18%、2039年には20%を超え、2055年に25%に達し、それ以降はほぼ同水準で推移します
この予想に対し、安倍政権は、国民の人口減少に対する危機感が高まっているとして、平成26年12月に「まち・ひと・しごと創生長期プラン」を閣議決定し、出生率を出来るだけ早く1.8に回復させ、2030~2040年頃には2.07まで回復させることにより、2060年の人口を1億人程度とし、2090年頃には人口を定常状態にする計画を作っています。
少子化問題の原因は何か
先述したように、1950年代に起こった少子化は、国が豊かになり死亡率が減少したことによって生ずるもの、歴史的必然とされています。また、1975年から1995年までの少子化は、世界的に人口を抑制しようという動きの中で、日本でも率先して「子どもは二人まで」という運動を行っていたからです。問題なのは、1995年以降の少子化です。1995年以降の少子化は、「若年層の経済的困窮」が引き起こしたと考えられています。
出生率は、有配偶率と有配偶出生率(結婚したカップルの子どもの数)、婚外子の3つの要因で説明できます。日本ではこのうち婚外子が少ないので、他の二つの要因が問題になります。有配偶出生率は落ちていません。完結出生率は2.2前後で推移しており、結婚したら二人の子どもを持つ慣行が崩れていません。一方有配偶率については、日本の結婚する意志をもつ未婚者は9割弱で、依然として高い水準にあるにもかかわらず、未婚率が非常に高くなっています。これは。若年層の経済的困窮に原因があると考えられています。
バブル経済と経済のグローバリゼーションを経て日本の雇用形態は大きく変化し、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマーなど、不安定で賃金の低い非正規雇用が増加しました。非正規雇用は20~24歳の若い年齢層で特に大きく割合を増やしました。「国民生活白書」(平成17年度)は、28~49歳の男性では年収400万円以下の層で独身者が多いと指摘しています。2010年の厚生労働省の調査によると、男性の場合30代の未婚率は正規労働者では30.7%、非正規労働者では75.6%と二倍以上です。なぜ、若者が結婚を控えるのか、家族社会学者の山田昌宏氏の考えを要約すると、「将来見込まれる結婚、子育てにおける生活水準が期待水準を下回ると、若者、特に女性は結婚や出産を控える」ということになります。この期待水準に含まれるのは、①住宅の広さと質、家電製品 ②子どもの教育、レジャー・趣味につかえるお金、そして ③自由な時間 です。
それでは、どうして若者に住宅、お金、自由な時間がないのでしょうか。まず、住宅事情について考えてみましょう。その根本原因は間違いなく、多くの人が大都市に集中して住んでいることです。政府による住宅補助がないという理由も大きいでしょう。また、若者が大都市に住むと、子育てを補助してくれる人が近くにいないことにもつながります。次いで、なぜ若者にお金がないのかです。これについては、詳しく述べ始めると、この本のバランスを崩してしまいますので、ここではキーワードだけに留めますが、グローバリゼーション、海外の企業・労働者との競争、他の世代特に高齢者との競争、日本の企業風土、非正規雇用の増加など勤労状況の悪化、東京一極集中、住宅費の高騰、高齢化に伴う社会保険料の高騰、などが重なっているためと考えられます。三つ目のなぜ自由な時間、家族との時間がないのかという点ですが、これもキーワードをならべると、住宅事情、遠距離通勤、企業文化、単身赴任、長時間労働、家庭での介護、などが重なっているからだと考えられます。ここで述べたことをまとめると、次の三つが少子化問題の根源にあると考えられます。
●大都市(東京)への人口集中
●海外の労働者や他世代(特に高齢者)との労働市場における競争、あるいは他世代の世話(介護、社会保険負担)
●日本の社員を大切にしない企業文化
政府はどう対応してきたのか
1972年の『成長の限界』を受けた形で、1974年に民間団体(人口問題研究会、日本家族計画連盟、家族計画国際協力財団、人口問題協議会)主催で日本人口会議がひらかれ、人口抑制をしなくてはならないと提言、新聞には「産児制限で人口増加に歯止め」「子どもは二人まで」と端的に書かれていました。そして、1974年の戦後二回目の人口白書には、人口が2010年から減少すると予測されていました。ところが、その当時には人口減少で何が起こるか、そして、人口減少をどのように食い止めるかという議論は全くされていませんでした。出口戦略を考えていなかったのです。現実は、1975年に合計特殊出生率が2を割り、そのときから「少子化」はスタートします。政府が対策として乗り出してくるのは1990年代に入ってからで、どこかで早くブレーキをかけるべきだったのですが、なかなか乗り出しませんでした。
政府は、1994年にエンゼルプラン「緊急保育対策5か年計画」を作って保育の量的拡大、低年齢児(0~2歳児)保育、延長保育、地域子育てセンター整備などを行いました。その後も、2003年に少子化対策基本法、2010年に少子化対策基本大綱、2012年に子ども子育て支援法などが施行されましたが、それらは人間の再生産の全過程を俯瞰したものではなく、「女性が子育てしにくい」という点だけに焦点を当てたものでした。そのため、キャリア女性を対象にした制度しかないとか、待機児童対策を長年しているが、少子化に歯止めがかからない、などの批判がなされています。政府が2014年に導入した「まち・ひと・しごと創生法」はもう少し広い視点からの少子化対策になっていますが、この内容については、日本の企業の状況、海外の政策について紹介してから述べることにします。
日本の企業にも、日本が少子化に落ち込んだことに関する大きな責任があります。1995年以降の少子化が、若年層の経済的困窮が最大の要因であり、その経済的困窮をもたらしたのが。経済のグローバル化のもとで、国内の雇用の非正規化をすすめていった企業と、それを許した政府にあることは明らかです。しかし、経済界はこの事実を正面から受け止めようとはしていません。少子化に関連して、日本経団連が意見を表明している資料として、2006年の『産業界・企業における少子化対策の基本的取り組みについて』があります。その内容をみると、少子化の深刻さについては認識しているものの、対応としては、働き方改革、男女共同参画、保育所の整備などの政府への要請にとどまり、自ら若年層の雇用条件を改善するスタンスは見えません。
次いで欧米諸国における少子化の状況についても述べておきましょう。
欧米の先進国では、1970年代に日本以上の不況に見舞われました。日本と同じように、「若年男性の収入の相対的低下」に直面しました。ヨーロッパの多くの国では日本以上に若年失業率は高まり、アメリカでは低賃金の雇用が増大しました。その結果、「若年男性一人の収入では、豊かな結婚生活を支えることはできない」という日本と同じ状況が出現しました。
アメリカやイギリスなどのアングロサクソン諸国でも1960年代までは、専業主婦が多く、男性一人の収入で妻子の生活を賄うことが一般的でした。ちなみに、1950年には、アメリカの既婚女性(高齢者を除く)の就労率は、25%程度、つまり、75%が専業主婦だったのです。日本では、既婚女性の労働力率は、下がっても四割だったので、アメリカは、日本以上の専業主婦社会だったのです。
アメリカでは、1970年代にフェミニズム運動が起きるとともに、女性の社会進出、つまり、職場労働への進出が起きます。フェミニズム運動は活発化し、その結果、雇用における女性差別が撤廃され、女性が十分な収入を得る職に就くことができるようになります。しかし、未婚女性が職に就いただけでは、少子化の歯止めにはなりません。アメリカでは、ベビーシッターをはじめとした子育て労働が市場によって供給されるようになりました。その結果、アメリカでは既婚女性の就労率は、2000年には、75%となります。
一方、北欧諸国では、公的に育児サービスが供給され、働きながら子どもを育てる条件が整います。育児や介護などの公共的事業は、母親を積極的に雇うことによって、育児サービスと母親の雇用の双方を作り出しました。多くの欧米諸国では、共働き化によって、若年男性の収入見通しの悪化を補ったのです。
こうして、欧米のほとんどの国々では、1970年代の少子化傾向が終了することとなりました。1980年代には、アメリカや北欧では出生率が回復し、フランスやイギリスなどでは少子化が止まりました。このように、欧米諸国では、社会全体の形を変えて少子化に対応しました、一方で日本はこの問題を単に女性の子育ての問題と小さくとらえ、抜本的な対応を行ってこなかったのだということが良くわかります。
日本政府が、子育て支援のレベルを超えてこの問題に取り組み始めたのが「まち・ひと・しごと創生法・長期ビジョン・総合戦略」(総合戦略)です。ここにはこれまでの政府の対策にはなかった斬新な考え方が含まれています。最も重要な指摘は、地方から都市への人口流出と、大都市における超低出生率が日本全体の人口減少につながっている、というもので、人口減少克服と地方創生を合わせて行おうとしています。この目的を達するために、サービス業、農林水産業、分散型エネルギーの推進により、地方で安定した雇用をつくり、地方への新しい人の流れをつくる、そのために地方移住者支援や、日本型CCRC(ケア付き退職者コミュニティー)をつくる、そして東京一極集中を是正しようとしています。もちろんこれは総合戦略ですから、それ以外のさまざまな手法、正社員実現加速や長時間労働の見直しなども書き込まれています。
しかし、この総合戦略の方向にそって現実の政治が動いているわけではありません。
農林水産業は、規模の大きい産業ではなく、また急激に規模拡大ができるものではありません。また、再生可能エネルギー分野では固定価格買取制度の買い取り価格が急激に引き下げられ、太陽光発電などからの収入を地域おこしに使う目論見は外れました。地方移住希望者は徐々に増えてはいますが、CCRCについては、現地に必要な介護施設や医療施設が不足していることなどが理由で、順調に立ち上がっている様子がありません。さらには、今後の少子高齢化に対応するためには人口の地方流出ではなく、都市をコンパクト化して都市の中央に人を集めるべきだという論者があらわれ、今後の方向性が見えなくなっています。さらには働き方改革の中心となる労働基準法の改正を中心とした「働き方改革関連法案」については継続審議が続いており、平成28年4月においても今後の見通しが立っていない状態であり、総合戦略が今後順調に実行に移されるか不透明な状態なのです。
これまでの政府の対応についてのコメント
これまでの政府の少子化問題に対する取り組みが保育や待機児童対策に偏っていたのは、問題の本質から目をそらし、問題を矮小化して、必要な対応を遅らせるものであるがゆえに、保育等の担当者の努力は、それなりに評価するとしても、全体としてとても褒められたものではないといえます。政府の少子化に取り組む姿勢に真剣さが足らなかったのは、日本が面積が小さいのに、人口が多すぎるという漠然とした感覚があり、環境危機、あるいは食糧・エネルギー危機の中で人口がある程度減少するのはむしろ好ましいことだという古い認識のままにいる方々が多かったからではないでしょうか。しかしながら、一定の「適正な人口」というものは本来存在せず、その時代の、テクノロジーや社会構造によって変化するのであり、縄文時代なら数十万人でもちょうどよかった人口は、農業の発展により、数千万人でも適正なものとなり、そこにエネルギーに関する技術の発達や、農業革命が加わると、日本列島は一億の人口でも支えられる国土となったのです。逆に、現在の少子高齢化や都市への人口集中の中で、日本の離島や地方は疲弊し、人体に例えると、まるで手足の感覚がなくなっていくように、日本という国の老化がすすんでいるように感じられます。そして、現在に至っては、日本は、少子高齢化による、社会保障の破たん、若者の負担増によるさらなる少子化、そして民族の消滅、亡国の危機に直面し、あらためて、少子化の恐ろしさに震え上がり、あるいは震え上がることさえもできずに無気力になっているのです。
私はこの本で、現在の日本の少子高齢化問題を、社会保障の問題、東京への一極集中の問題と同時に解決するための「試案」を示しますが、そこに至る前に、日本政府と企業に対し、「日本人の思考方法、行動パターン」が、現代の日本の少子化問題をはじめとする社会問題を生み出した、ということを訴えておきたいのです。この問題点をしっかりと認識し、あるいは日本の社会構造の中に組み込んでおかないと、日本はまた同じ過ちを繰り返し、世界の中で生きていけない国になるからです。それはこういうことです。
●国民に「犬の道」を歩かせて、精神論で国民の尻を叩いてはなりません。
「犬の道」とは、ヤフー・チーフ・ストラテジーオフィサー安宅和人氏の著書『イシューからはじめよ』に紹介されている言葉ですが、「優先順位を考えず、一心不乱に大量の仕事をして目標に達しようとする」手法のことです。戦時中の「風船爆弾」や「竹やり」ではありませんが、「保育システム」だけを使って少子化に対応しようとしたり、「年金等の国民負担を極端に引き上げ(例えば国民負担率85%)、あるいは国民への支給を極端に遅らせて(年金支給開始75歳)」少子高齢化に対応しようとしたりするのがこれにあたると思われます。国民がどんどん疲弊し、少子高齢化が止まることはありません。国民に努力しなさいと、大号令をかける前に、問題の本質をつかみ、より楽に目標を達成できる別の道がないか、公の場でもっと広く議論すべきです。
●子どもや若い世代を大切にしなくてはなりません。
日本の現役世代向けの社会保障は、欧米の1/2~1/3しかありません。日本の社会保障の給付費は年金と医療で約8割を占めます。医療費のうち65歳以上が全体の58%を占め、現役世代とは1人当たりで4倍の開きがあります。子育てや職業訓練・紹介などが充実し、現役世代と高齢者の給付費が均衡しているスウェーデンなどの北欧諸国とは雲泥の差なのです。「大切なものを、大切と言い続け、守る勇気」が社会に足りないのでしょう。住宅補助についても、日本では制度がありません。これは、日本では終身雇用を前提として、企業が社宅や住宅補助を行っていたためです。終身雇用がなくなっても、国の補助制度がないままなのです。ヨーロッパの住宅補助は、イギリスは全世帯の1/6に対して平均52万円の補助が、フランスは全世帯の1/4に対して平均28万円の補助があります。
●政府が自国通貨を積み立てることは将来に備えることを意味しません。
国が亡ぶとき、国の通貨の価値も同時になくなることを考えると、「自国通貨は国にとって価値でない」ことが分かります。それであるなら、「将来の年金のために、国民から自国通貨を集め、積み立てておく」ことは、政府の帳簿上にはプラスであっても、国富を増やさず、国民を痛めつけ、結果的に国の富を減らすことになってしまいます。それでは、一体、今何をしておけば、国富を増やし、少子高齢化に対応することになるのでしょうか? それは本の後半でしっかりと議論したいと思います。